-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
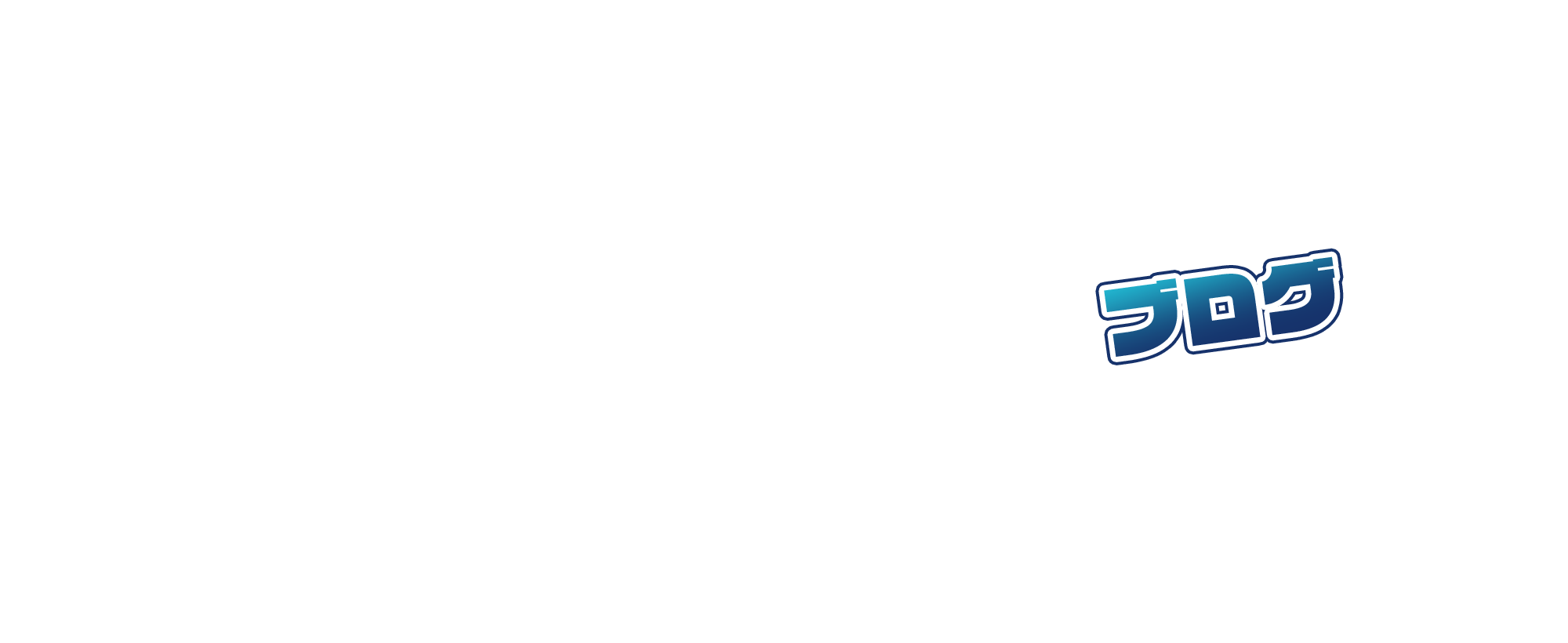
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
梁は曲げとせん断の複合応力に晒されます。端部は曲げモーメントが大きく、上端筋が主役。同時にせん断力に対してスターラップが梁を“帯”のように締め上げます。ここでは、梁の施工順序・干渉回避・検査ポイントを体系化します。🧠
1) 施工順序の原則
1. ハンガー筋→2. 下端主筋→3. スターラップ通し→4. 上端主筋→5. 配力筋・補強筋。
• 先にスターラップを“通す”ことで、上端の浮きやかぶり不足を抑制。
2) 端部の密配筋と定着
• 端部@:設計で@50〜@100などの緊密部が指定される。区間の始まり・終わりを間違えないよう、スプレーテープで現場表示。
• 定着:梁端の上端筋は柱内定着。折返し(フック)の長さ・方向を加工帳に明記。
• ハンチ・段差:折返し位置とスターラップの角度に注意。ハンチ部はスターラップ角度変更の指示を見落としがち。
3) 開口・スリーブ周り
• 開口補強:開口周囲1D/2D/3Dの範囲で増し筋。四隅のL形補強を忘れない。
• スリーブ干渉:設備と三者調整。丸鋼スペーサーで仮保持→スターラップで抱かせる。
4) かぶりとスペーサー
• 梁側面は型枠押しが強い。側面スペーサーとタイバンドで逃げないよう保持。
• サドルスペーサーで上端筋の高さを一定に。
5) よくあるNG
• スターラップの向き・継手位置がバラバラ→継手は交互ずらし、向きは統一。
• 上端筋の“浮き”→結束の締め過ぎor不足。ハンガー筋を活用して“水平”を出す。
• 端部密配筋に“増し結束”不足→打設時に崩れる。増し結束をルール化。
6) 写真の撮り方
• スターラップ@の密・疎境界にテープを貼って写すと第三者に明快。
• 柱内定着の“入り”が分かる角度で。
現場チェックリスト ✅ – 施工順序は“スターラップ通し→上端”の原則になっている? – 端部の@境界は表示した? – 柱内定着の長さ・方向は加工帳に明記? – 開口補強は範囲・本数ともOK?
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
柱は建物の“背骨”。主筋が軸力・曲げを受け、帯筋(フープ)がコアコンクリートを拘束し、座屈を抑えます。耐震性能の肝は、実は帯筋のピッチ・継手・フックの三拍子。ここでは、施工で外しやすい勘所を徹底的に潰します。💥
1) 段取りと墨出し
• 柱芯の確認:通り芯×直交芯。型枠前に“墨+釘+写真”でエビデンス。
• 主筋の建て込み:建入れ(垂直)はレベルと下げ振りでWチェック。揚重+仮筋交いで直立保持。
2) 帯筋(フープ)の鉄則
• 端部処理:135°フックが基本。柱コーナー外側で重ね、継手位置を上下でずらす。
• ピッチ:端部(柱梁接合部近傍)は@50〜@100の緊密配筋、中央は@100〜@150が一般的(設計に従う)。
• 中子(内法):主筋の座屈支点を短くするよう中子筋を配置。
• かぶり:スペーサーブロックを四周で計画的に。型枠押しでズレやすい面は増し。
3) 継手・定着
• 主筋継手:重ねは同一断面集中NG。1/4以上ずらすを徹底。機械式はトルク管理・マーキングを必ず。
• 定着:柱頭・柱脚の定着長は梁・基礎に食い込む。“梁主筋の邪魔”にならない3D段取りが鍵。📐
4) 柱梁接合部の詰め方
• 梁上端筋の折返しと柱帯筋の通しが干渉。→ 順序:柱帯筋→梁主筋→追加帯筋の“入れ子”。
• ハンガー筋で上端筋を一時保持、サドルスペーサーでかぶり確保。
5) ありがちNG
• 帯筋フックの向きバラバラ→統一方向で検査写真に写るよう配慮。
• スペーサー不足でかぶり欠損→柱四隅は増し、1m角で最低4個を目安。
• 主筋の建入れ不良→束ね・クランプで矯正。梁型枠建込前に必ず是正。
6) 写真の撮り方
• 通り芯・フック角・ピッチが一枚に入る“斜め”ショット。
• 継手位置のずらしはマーキングで可視化。
現場チェックリスト ✅ – 帯筋の端部フックは135°?位置は統一? – 継手集中していない?(ずらしOK?) – 柱頭・柱脚の定着長は確保? – かぶりスペーサーは規定ピッチで置いた?
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
安全はスローガンではなく生産性。ヒヤリハットを潰す仕組みは、段取りの良さと同義です。この回では、鉄筋工事特有のリスクと、KY(危険予知)・TBM(ツールボックスミーティング)の“回し方”を、テンプレ付きで解説します。
1) 主要リスクと対策
• 墜落・転落:床開口、端部作業、足場の不整備。→ フルハーネス、親綱、開口の即日養生、声かけ運動。
• 飛来落下:切断端、工具、束材の転倒。→ 落下防止コード、荷揚げ計画、二人作業。
• 挟まれ・巻き込まれ:ベンダー、カッター、クレーン搬入。→ 作業半径内の立入禁止、合図者の明確化。
• 切創:バリ、番線の端。→ 耐切創手袋、バリ取り徹底。
• 熱中症:夏季はWBGT表示、塩分・休憩ローテ、氷嚢。
• 粉じん・騒音:切断・斫り時の集じん・耳栓。
• 感電・火災:延長コードの被覆破損、火花養生不足。→ 毎朝の目視点検、消火器の近接配置。
2) KY/TBMの“型”
• 5分前集合→5分で回す:長い会議は現場に効かない。短く、毎日。
• フォーマット:①今日の作業 ②危険ポイント ③対策 ④役割分担 ⑤合図・指差呼称 ⑥終業点検
• 例(梁端部スターラップ@100取付)
o 危険:端部の墜落、ハンマー誤打、番線端の刺創
o 対策:親綱・二丁掛け、打撃方向の確認、番線端の折返し
o 役割:A上筋、Bスターラップ、C結束、D監視
o 合図:「固定」「締め」「良し」で声掛け
3) ヒヤリハットの共有
• “責めない文化”が前提。週1でベスト&ワーストを掲示板共有→是正を写真化して横展開。
• KYT(危険予知訓練):写真1枚から危険要因を3つ挙げ、対策を1行で書くトレーニング。
4) 季節・現場条件別のポイント
• 夏:休憩増+打設日程の前倒し検討。午後イチに重作業を置かない。
• 冬:凍結で足場・スペーサーが滑る。滑り止めと保温。
• 雨:納材の防錆養生、滑り対策。濡れた番線は手袋に刺さりやすい。
5) 緊急時対応フロー
1. 作業中止→安全確保
2. 応急処置→救急連絡(119)
3. 現場責任者へ報告→写真・状況記録
4. 原因分析→再発防止→朝礼共有
TBMメモ
“昨日の学び”を1行発表→“今日のリスク”を3つ→“対策宣言”を全員で声出し。たった3分で現場の事故率は目に見えて下がります。
安全チェックリスト ✅ – 開口部に即日養生・幅木・標識がある? – 延長コード・グラインダの被覆は無傷? – WBGT値と休憩ローテは掲示した? – 合図者は決まっている?
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
鉄筋工事の仕上がりは、図面と加工帳の正確さだけでなく、結束・切断・曲げという“最後の一手”の質で決まります。ここを疎かにすると、配筋は寸法通りでもコンクリートの打込み時に崩れる・かぶりが消える・定着が足りないといった事故につながります。今回は、現場標準となる手順・判断基準・小ワザを体系化してまとめました。✨
1) 結束(タイイング)の基本
• 番線の種類:#16(φ1.6)、#18(φ1.2)を使い分け。荷重の掛かる箇所や仮固定にはやや太めを。
• 結束の型
o クロス結束(×):交点固定の基本。作業性がよく、全体の“ゆとり”を残せる。
o サドル結束(Π):主筋を跨いで押さえる。上端筋の浮き防止に有効。
o ツイスト結束:素早いが、締め過ぎは位置ズレの原因。締め代を意識。
o ハリガネ喰い込みNG:防錆の観点からも、ねじ切りは避けたい。
• 結束ピッチの考え方:図面の@ピッチとは別に、施工上の結束間隔を設定。目安は300〜400mm、コーナー・継手・端部は増し結束。
• 電動結束機の使い所:面積の大きいスラブ・壁で生産性◎。ただし狭い梁端・柱梁接合部は手締めの方が確実なことも。
現場TIPS
結束は“固定”ではなく“保持”。調整の余地を残す締め加減が、最終のかぶり・定着を守ります。
2) 切断(カッティング)の勘所
• 工具:油圧カッター、ディスクグラインダ、レシプロソー。火花養生と切粉回収を徹底。
• 切断端の処理:バリ取りは必須。手袋で引っ掛ける事故防止&定着長の正味確保。
• 寸法の追い込み:“長めに切って現場合わせ”は禁止。加工帳は正寸で作り、現場は“置き方の工夫”で吸収。
• 安全:切断面の飛来落下、火気、延長コードの被覆破損に注意。切断時は火花方向に人を立たせない。
3) 曲げ(ベンディング)の品質
• 曲げ半径R:最小Rは鋼種・径で規定。小さすぎると脆性破断のリスク。曲げ冶具のピン径で管理。
• バネ戻り:鋼種が上がるほど戻る。5〜10°多めに曲げ→現場合わせ。
• 二度曲げ:原則避ける。やむを得ない場合は監理者承認+再曲げ規定の範囲で。
• 端部のフック:135°/90°の角度・長さを明記。“曲げ角だけ指示”は誤解の元。
• ねじれの除去:曲げ後に面がくるよう矯正。ねじれはかぶり不足・スペーサー脱落を招く。
4) 加工帳(バーリスト)の作法
• 記載要素:部位/番号、径、鋼種、L、曲げ角、R、数量、備考(定着・継手・端部処理)。
• 歩留まり最適化:原尺と曲げ材の“巣組み”でロス最小化。D13×6mを例に、1500/1800/2100の組合せ最適を試算。
• 識別管理:色ラベル+QRで図番紐付け。束ごとに札を必ず付ける。
5) ありがちNGとリカバリー
• 締め過ぎで位置ズレ→“仮締め→最終締め”の二段階に。
• 曲げR不足→冶具のピン径を定期確認。自作冶具は基準化。
• バリ残り→“切断→バリ取り→結束”を一人一工程にせず、ペアで相互確認。
• 開口補強の範囲間違い→“開口径の何D”をマスキングテープで現場可視化。
6) 写真と記録
• 曲げ端部の角度・長さが写る“斜め45°”を入れる。
• スペーサー高さはスケールを添えて。かぶりの根拠写真に。
現場チェックリスト ✅ – 番線の使い分けがチームで統一されている? – 曲げ冶具のピン径・角度ゲージは点検済み? – 加工帳の番号札は束に付いている? – 切断火花の養生・立入禁止はOK?
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
良い配筋は、始まる前に8割決まります。段取りと品質管理は“習慣化”が命。ここでは、材料→加工→据付→検査→是正→引継の一連を、誰が・いつ・どこで・何をで抜け漏れなく回す方法を紹介します。
1) 材料手配と受入
• 加工帳(BBS)を起点に発注。長尺・曲げの歩留まり最適化でコストを圧縮
• 納品時は鋼種(SD)、径、長さ、マーキングを確認。ミルシートを添付保管
• 仮置きは“先に使うものほど手前”の原則。動線を塞がないレイアウトに
2) 加工と識別
• 曲げ半径R・角度を遵守。再曲げは原則避ける(必要なら監理者確認)
• 束ごとにタグを付け、部位・径・数量・図番を明記。色テープで識別
3) 据付と結束
• スペーサー(サイコロ/サドル/チェア)を適切ピッチで。かぶり厚は“実測”で確認
• 結束は端部・交点・中間のメリハリ。全部を固めすぎると調整不能⚖️
4) 自己検査→立会検査
• 寸法(芯々、開口位置)、ピッチ、継手位置のずらし、定着長をチェック
• チェックリストは“写真の必須カット”とセットで用意(例:定規・通り芯・メモが一枚に収まる構図)
• 是正は“なぜ起きたか”まで遡及。治す→再発防止がワンセット
5) よくある是正とコツ
• かぶり不足:スペーサー追加・位置替え。型枠押しの癖がある箇所は、タイバンドで保持
• ピッチ不良:ゲージ活用+終端の半ピッチ調整。目標線を墨出しで用意すると迷わない
• 定着不足:フック長を再確認。梁端部は特に過密で見落としがち
6) 写真・記録の整備
• 撮り漏れは後戻りの源。部位→詳細→全景→通り芯入りの順で固定化
• データは図番フォルダで管理。是正前/後を並べられる命名規則に️
7) チームで強くなる仕組み
• 朝礼TBMで“きのうの学び・きょうのリスク”を30秒で共有
• 良い写真・良い段取りは掲示板(社内チャット)で称賛→真似が広がる
• 新人には“目的→根拠→作業”の順で説明。意味が分かれば手が正確になる
現場チェックリスト ✅ – ミルシート・納品書はファイル化した? – スペーサー数量は“かぶり×ピッチ×面積”で逆算した? – 立会検査の必須カットと是正締切は共有できてる? – 是正の“原因・対策・再発防止”を3行で記録した?
________________________________________
※第5回以降(工具・治具/安全衛生/柱・梁・スラブ・壁の要点/基礎配筋/継手/かぶり・定着/加工帳/工程管理/防錆/取り合い/検査写真/コスト・歩掛/BIM・効率化/品質事故/人材育成/未来の鉄筋工事)は、同じトーンで順次公開予定です。
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
配筋図を前に“固まる”最大の理由は、平面・立面・断面の切替に慣れていないから。そこで今回は、図面を地図のように読むコツを伝授します。目的地(部位)を決めて、道(経路)をたどり、標識(記号)を解釈する——それだけで視界はクリアになります。🧭
1) 地図としての“平面図”
• スラブや梁の平面図は“上から見た写真”。梁芯・スラブ開口・スリーブ位置が一望できます
• ハッチングや太線/細線で部材の優先度が表現されることも
• 記号例:S梁(スラブ上の小梁)、BM(梁番号)、G(グリッド/通り芯)
2) 立面図・断面図で“高さ”をつかむ
• 立面図は横から見た側面図。TOP/BOT、段差、折返しが理解しやすい
• 断面図は“切って中身を見た”図。フープ@100、スターラップ@150など密度の確認に最適
• レベル記号(±0、GL、FL)で高さ基準をつかむ。スペーサー選定の根拠にも📏
3) 表記の“文法”
• D16@200:D16を200mmピッチで並べる
• 2-D19 TOP:上端にD19を2本
• L=1500 135°フック:長さ1500、端部は135°で定着
• ≒や≈:概略寸法。実施設計ではNG、施工では“調整可”のニュアンス
4) 図面読みの手順(実践)
1. 対象部材を決める(例:2F大梁BM-2)
2. 平面図で範囲を把握(スパン、支点、開口)
3. 断面図で鉄筋密度・定着・かぶりをチェック
4. 詳細図・部分拡大で端部処理・折返し・段差処理を確認
5. 加工帳に落とす(曲げ角度、R、L、フック長、数量)
5) よくある読み間違い
• @の基準:梁・柱の中心線基準か、面基準か。数量・加工長にズレ
• 開口補強の“範囲”:開口周囲1D/2D/3Dの規定見落とし
• スラブ上端のレベル:かぶり分の浮かせを忘れて上端が沈む🏚️
6) BIMや3Dで“立体の感覚”を育てる
紙だけで迷うなら、模型・3Dビューで理解を一気に進めるのも手。干渉チェックや開口補強の“効き”が視覚的に共有できます。スマホでAR表示できるアプリも増え、現場の“共通言語”に。📱
現場TIPS ✍️
図面は“地図”。現在地(今どの図面のどこを見ている?)と目的地(何を決めたい?)を声に出して確認しながら進めると、読み間違いが激減します。
7) 検査写真に強い図面メモの作り方
• 写真に映る位置へ通り芯・BM番号を小さく書き込む
• ピッチゲージで@確認、スケールでかぶり提示
• フック角度や定着長は“指差し”で写すと第三者にも伝わる📸
まとめ
配筋図は“文法”と“視点”が分かれば怖くありません。次回は、図面を手に段取り→配筋検査までの品質管理フローを、チェックリストとともに解説します。🧭✅
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
現場で「D13、SD345、@200、フック135°」と飛び交う言葉。初見では暗号ですが、一度“文法”をつかめば一気に読み解けます。ここでは径(D表記)、強度(SD表記)、用途部材、表面処理、継手方式まで、図面を読み解くための“鍵”を整理します。🗝️
1) 径の表記:D10〜D51
• DはDeformed(異形棒鋼)の頭文字。数字は呼び径(mm目安)
• 現場頻出:D10/13(配力・スターラップ)、D16/19(主筋)、D22/25/29(大ばり・柱主筋)、D32以上(大断面)
• 曲げ半径Rは径に比例して大きくなる。小さすぎると脆性破断のリスク⚠️
2) 強度区分:SD295/345/390/490…
• SD=Steel Deformed。数字は降伏点(N/mm²)のおおよそ
• 使い分け:一般RCはSD295/345が主、耐震要件の厳しい部位はSD390以上も
• ミルシート(製造証明)で規格確認。受入時は鋼種の取り違いに注意🔍
3) 表面の種類
• 異形棒鋼(リブ有):付着力が高い標準品
• 丸鋼(平滑):付着力は低いが、引張の効く部位では基本NG。用途限定
• エポキシ樹脂塗装・溶融亜鉛めっき:腐食環境での耐久性アップ。ただし付着低下補正や曲げ加工可否の確認が必要🧪
4) 部材別の俗称と役割
• 主筋:曲げ・引張を負担する“主役”
• 配力筋:主筋直交方向のひび割れ抑制・力の分散
• スターラップ/あばら筋:梁のせん断補強
• フープ/帯筋:柱の拘束、座屈防止
• スラブ上端/下端筋:曲げ・温度収縮対策
5) 記号の読み方・例文
• @200:200mmピッチ
• 2-D16:D16を2本
• L=1500:長さ1500mm
• TOP/BOT:上端/下端、↑/↓矢印で段差や折返し
• フック135°(or 90°):端部処理の角度、定着長さは径×規定係数で算定
6) 継手の種類
• 重ね継手:簡便だが配置のずらしが必要(同断面同位置に集中はNG)
• 溶接継手:管理手間が大、適用範囲限定
• 機械式継手:専用カプラで軸力伝達、トルク管理・抜取りが必須
7) 図面と現場の“ズレ”を埋めるコツ
• 加工帳(BBS)に“曲げ角度・R・定着”を明記し、曲げ回数の制限も共有
• 色分けラベルで径・鋼種の取り違いを撲滅(D16=青、D19=赤…など現場ルール)
• 干渉予測:特にスリーブ・インサートは早期に3者(型枠/設備/鉄筋)で摺合せ🤝
ワンポイント💡
D13とD16の“ちょっとの差”が、曲げRやフック長さ、スペーサー高さに波及します。一つ上の径に変わるとすべての段取りが微妙に変わる——ここを最初に押さえると現場が落ち着きます。
まとめ
図面の暗号は、D(径)×SD(強度)×@(ピッチ)×L(長さ)×端部処理で読み解けます。次回はこの記号が並ぶ配筋図そのものの“読み方”を、上から見る/横から見る/切って見るの3視点で徹底的に解説します。📐✨
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
コンクリートは圧縮には強いけれど、引張には弱い——この“弱点”を補うのが鉄筋です。鉄筋工事とは、設計図どおりに鉄筋を加工・運搬・組立(配筋)し、所定の位置と寸法精度で固定する仕事。完成後はコンクリートに覆われ見えなくなりますが、建物の“骨”として耐震・耐久性能を大きく左右します。だからこそ、見えなくなる前の品質が命。ここを外すと、後でどれだけ修繕しても取り返しがつきません。💡
RCの仕組みをカンタンに
• 圧縮に強い: コンクリート(Cr)
• 引張に強い: 鉄筋(Rebar)
• 熱膨張が近い: Crと鉄は温度変化での伸び縮みが近く、複合材として相性が良い
• 付着: コンクリートの凸凹に鉄筋のリブが“噛む”ことで力が伝わる
この“付着”が効くためには、適切なかぶり厚さ(コンクリートの被覆厚)と定着長さが必要。また、錆は全部が悪ではありません。ミルスケールの上にうっすら付く“健全な錆”は付着に寄与する一方、フレーク状で剥離する赤錆や、油・泥の付着はNG。現場では錆の見極めも重要なスキルです。🧐
鉄筋工事の主な工程(ざっくり)
1. 施工計画・段取り:図面・加工帳(BBS)作成、材料手配、工程表作成
2. 受入・検収:材質・径・本数・表示をチェック、保管・識別、雨養生
3. 加工:切断・曲げ(ベンダー/カッター、曲げ半径Rの遵守)
4. 配筋:スペーサー設置→主筋・あばら筋・フープ・スターラップ据付
5. 結束:番線#16/18などで結束(ツイスト/サドル/クロス)
6. 自己検査→監理者/第三者検査:寸法・ピッチ・かぶり・継手・定着
7. 是正→再検査→型枠・打設へ:写真記録を整備し引き継ぎ
現場で“効く”心構え
• 先行段取り=品質:材料の仮置き動線、揚重計画、通路確保で“作業の良いリズム”を作る
• 図面の統合理解:構造図/配筋詳細/意匠/設備の整合。特にスリーブ開口は干渉の温床🚧
• 見える化:色テープで径を識別、加工済み束を番号札で管理、検査写真は“誰でも分かる”角度で📸
よくあるNGとリカバリー
• かぶり不足:スペーサー不足、型枠への押付け。→ 追加スペーサー、結束やタイバンドで保持。写真で再発防止共有
• ピッチ違い:@100が@125に… → ピッチゲージで自主管理、終端で“半ピッチ調整”
• 定着不足:フック角度/長さ不足。→ 再加工(曲げ直しは曲げ半径・回数の規定に注意)
まとめ
鉄筋工事は“見えなくなる品質”を作る仕事。段取り・図面理解・安全衛生が合わさって、初めて良い配筋が仕上がります。次回は、現場でよく出る鉄筋の種類と記号を、写真がなくてもイメージできる言葉で解説します。🔍✨
現場ミニチェックリスト ✅ – 図面・加工帳と納品材の照合は誰が/いつ/どこで? – 鉄筋の仮置きゾーンと動線は干渉しない? – スペーサーの種類/数量/ピッチは足りてる? – 検査写真の必須カットは一覧化した?
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
さて今回は
~チェックリスト&不具合ゼロのコツ~
「写真は足りてる?」「指摘が毎回同じ…」——配筋検査の“モヤモヤ”を解消するために、そのまま使えるチェックリストと指摘が消える現場ルールを公開。検査の再現性を上げて、是正・再検の手間を減らしましょう。📒✨
施工図・配筋図・加工図の一致(最新リビジョンか)
鉄筋径・本数・ピッチ(マーキングで見える化)
かぶり厚さ(スペーサー種・配置ピッチ)
継手位置(千鳥・集中回避/禁止ゾーン遵守)
定着長さ(折曲げR・フック形状)
結束状態(交点抜け・緩み無し)
開口補強(スリーブ・スリット周り)
清掃(型枠内のゴミ・切屑ゼロ)
TIP💡:部位ごとに色スプレーでマーキング(梁=青、柱=赤、スラブ=黄など)→検査スピードUP。
帯筋ピッチの乱れ/フックの向き間違い → 基準墨の見える化
継手集中 → 高さ方向で分散、機械式継手も検討
スターラップの端部処理・余長不足 → 折曲げ寸法の再確認
梁端定着の“入り逃げ”不足 → 先組み&仮留めで確保
端部補強筋の入れ忘れ → 開口・端部は別紙で強調
椅子間隔が広すぎ→たわみ→かぶり不足に直結
検査前日に自主検査→是正→写真撮影を完了
密部テンプレ(梁端・柱頭・開口部)の定型写真を用意
指摘履歴をチェックリストに落とし込み再発ゼロ化
デカスケール&白チョークで寸法が写真に写る化
指差し呼称:「スターラップ向き良し、ピッチ良し、かぶり良し」🗣️
全景→部位→寸法アップの三段構成
写真名は「日付_工区_部位_内容」
是正後は同アングルで再撮→Before/Afterが一目で分かる
かぶり不足:椅子追加/スペーサー高さ交換
継手かたより:数本抜き替え→千鳥へ
結束緩み:二重結束で再発防止
曲げ寸法違い:場内再加工は安全第一、無理はNG
直前:清掃→通し見→写真の順で抜け漏れゼロ
打設中:バイブレータの当て過ぎNG、鉄筋移動に注意
打設後:天端均し中にスペーサー外れが無いか再点検
バーコード管理でロット追跡
クラウド写真台帳で共有スピードUP
チェックリストのフォーム化(スマホ入力→PDF自動出力)📑
配筋検査は“型化”すれば怖くない。チェックリストと写真運用を整えるだけで、是正回数・再検回数が確実に減ります。現場の実情に合わせたテンプレ提供や教育同伴も行っています。お気軽にご相談ください。📞✨
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
さて今回は
~段取りと品質管理~
柱・梁・スラブ——建物の“骨”をつくる鉄筋工事は、段取り8割。加工図から搬入、建て込み、配筋検査、コンクリート打設までの勝ちパターンを、現場目線でわかりやすくまとめました。初めての方にも、品質と安全を両立できる実務のコツをご紹介します。✨
施工図・加工図の整合:断面記号・定着長さ・折曲げ寸法を相互チェック
バーリスト:径・本数・長さ・形状を整理し、加工場と納期を確定
干渉確認:スリーブ・インサート・設備配管と早期に調整(開口補強筋の有無)
ワンポイント:梁端・柱頭の定着・継手集中は混みやすい。先に“密箇所の段取り”を決めると後が楽に。
ロット表示・色分けタグで現場混在を防止
水平養生&端部保護で曲がり対策
表面錆はワイヤーブラシで除去、異物付着はNG
ハンガー筋・馬筋・椅子(スペーサー)でかぶり厚さを確実に確保
結束ピッチは設計・仕様に従い、交点抜けゼロへ
スターラップの向き・継手位置の千鳥配置を徹底
よくあるNG⚠️:スペーサーブロックの不足、端部のゲタ落ち。打設前の通し見で必ず拾う。
重ね継手:コスト◎、ただし重ね長さと配置に注意
圧接継手:性能◎、火気管理・記録が要
機械式継手:省スペース◎、特に密配筋部や柱梁接合部で有効
判断軸:施工性×スペース×要求性能。密集部は“細径多本数→太径少本数化”も検討。
梁端部:上フックの入り逃げを確保、はらみ防止に番線仮留め
柱帯筋:ピッチと端部フックの向き確認
スラブ端部:見切り・開口周りの補強筋を忘れずに
自主検査(下請)→写真・スケール入りで記録
元請/設計検査→指摘是正
再検査→是正完了写真を追記し、打設GO
写真は「全景→部位→寸法アップ」の3段構成が鉄板。
歩み板で鉄筋踏み抜き防止
バイブレータは鉄筋接触NG(移動・変形の原因)
打設中のかぶり確認・スペーサー落ち再点検
墜落・転落対策:手摺先行・親綱・フルハーネス
切創対策:端部養生キャップ・手袋の選定
端材分別:鉄スクラップ回収で資源循環♻️
鉄筋工事は、図面整合→搬入→建て込み→検査→打設の段取り勝負。基本を徹底するだけで、手戻りとクレームは激減します。現場の状況に合わせた密部の解消計画や継手選定も、お気軽にご相談ください。
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()