-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
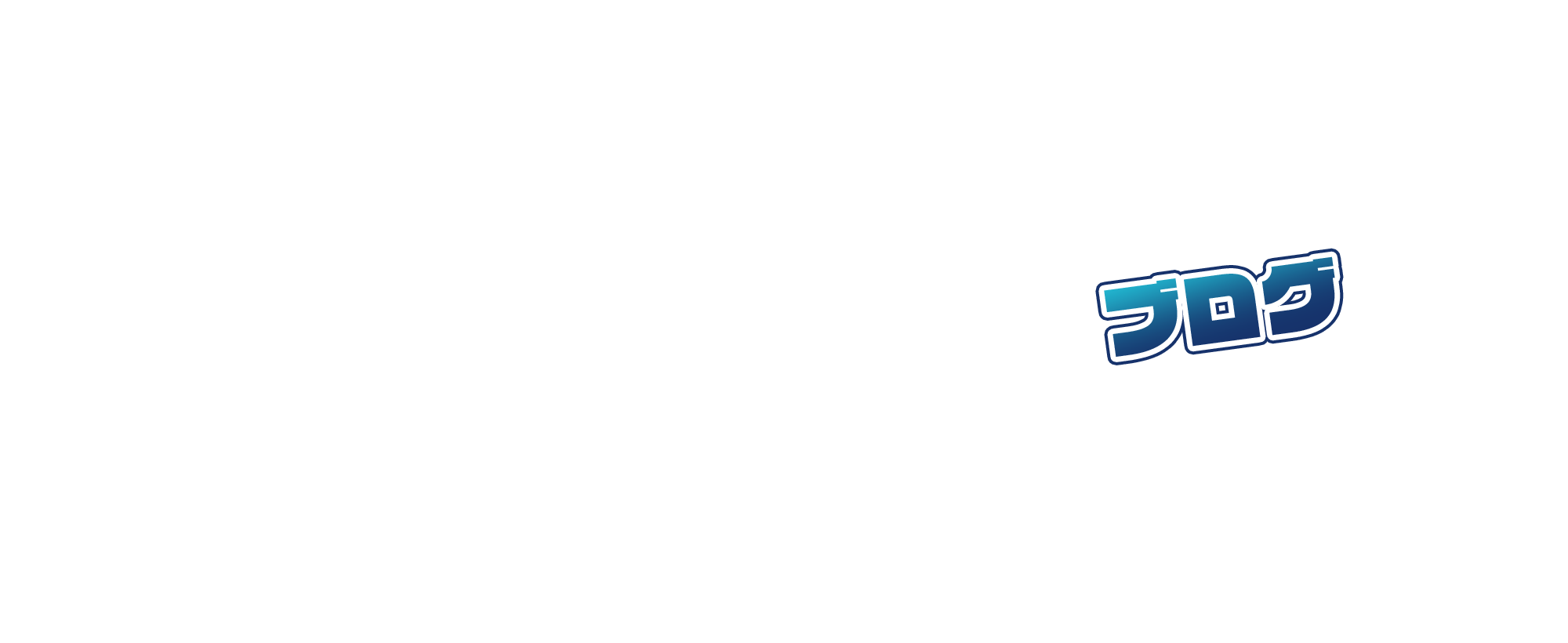
皆さんこんにちは!
株式会社フテン、更新担当の中西です。
鉄筋工事の仕上がりは、図面と加工帳の正確さだけでなく、結束・切断・曲げという“最後の一手”の質で決まります。ここを疎かにすると、配筋は寸法通りでもコンクリートの打込み時に崩れる・かぶりが消える・定着が足りないといった事故につながります。今回は、現場標準となる手順・判断基準・小ワザを体系化してまとめました。✨
1) 結束(タイイング)の基本
• 番線の種類:#16(φ1.6)、#18(φ1.2)を使い分け。荷重の掛かる箇所や仮固定にはやや太めを。
• 結束の型
o クロス結束(×):交点固定の基本。作業性がよく、全体の“ゆとり”を残せる。
o サドル結束(Π):主筋を跨いで押さえる。上端筋の浮き防止に有効。
o ツイスト結束:素早いが、締め過ぎは位置ズレの原因。締め代を意識。
o ハリガネ喰い込みNG:防錆の観点からも、ねじ切りは避けたい。
• 結束ピッチの考え方:図面の@ピッチとは別に、施工上の結束間隔を設定。目安は300〜400mm、コーナー・継手・端部は増し結束。
• 電動結束機の使い所:面積の大きいスラブ・壁で生産性◎。ただし狭い梁端・柱梁接合部は手締めの方が確実なことも。
現場TIPS
結束は“固定”ではなく“保持”。調整の余地を残す締め加減が、最終のかぶり・定着を守ります。
2) 切断(カッティング)の勘所
• 工具:油圧カッター、ディスクグラインダ、レシプロソー。火花養生と切粉回収を徹底。
• 切断端の処理:バリ取りは必須。手袋で引っ掛ける事故防止&定着長の正味確保。
• 寸法の追い込み:“長めに切って現場合わせ”は禁止。加工帳は正寸で作り、現場は“置き方の工夫”で吸収。
• 安全:切断面の飛来落下、火気、延長コードの被覆破損に注意。切断時は火花方向に人を立たせない。
3) 曲げ(ベンディング)の品質
• 曲げ半径R:最小Rは鋼種・径で規定。小さすぎると脆性破断のリスク。曲げ冶具のピン径で管理。
• バネ戻り:鋼種が上がるほど戻る。5〜10°多めに曲げ→現場合わせ。
• 二度曲げ:原則避ける。やむを得ない場合は監理者承認+再曲げ規定の範囲で。
• 端部のフック:135°/90°の角度・長さを明記。“曲げ角だけ指示”は誤解の元。
• ねじれの除去:曲げ後に面がくるよう矯正。ねじれはかぶり不足・スペーサー脱落を招く。
4) 加工帳(バーリスト)の作法
• 記載要素:部位/番号、径、鋼種、L、曲げ角、R、数量、備考(定着・継手・端部処理)。
• 歩留まり最適化:原尺と曲げ材の“巣組み”でロス最小化。D13×6mを例に、1500/1800/2100の組合せ最適を試算。
• 識別管理:色ラベル+QRで図番紐付け。束ごとに札を必ず付ける。
5) ありがちNGとリカバリー
• 締め過ぎで位置ズレ→“仮締め→最終締め”の二段階に。
• 曲げR不足→冶具のピン径を定期確認。自作冶具は基準化。
• バリ残り→“切断→バリ取り→結束”を一人一工程にせず、ペアで相互確認。
• 開口補強の範囲間違い→“開口径の何D”をマスキングテープで現場可視化。
6) 写真と記録
• 曲げ端部の角度・長さが写る“斜め45°”を入れる。
• スペーサー高さはスケールを添えて。かぶりの根拠写真に。
現場チェックリスト ✅ – 番線の使い分けがチームで統一されている? – 曲げ冶具のピン径・角度ゲージは点検済み? – 加工帳の番号札は束に付いている? – 切断火花の養生・立入禁止はOK?
株式会社フテンでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()